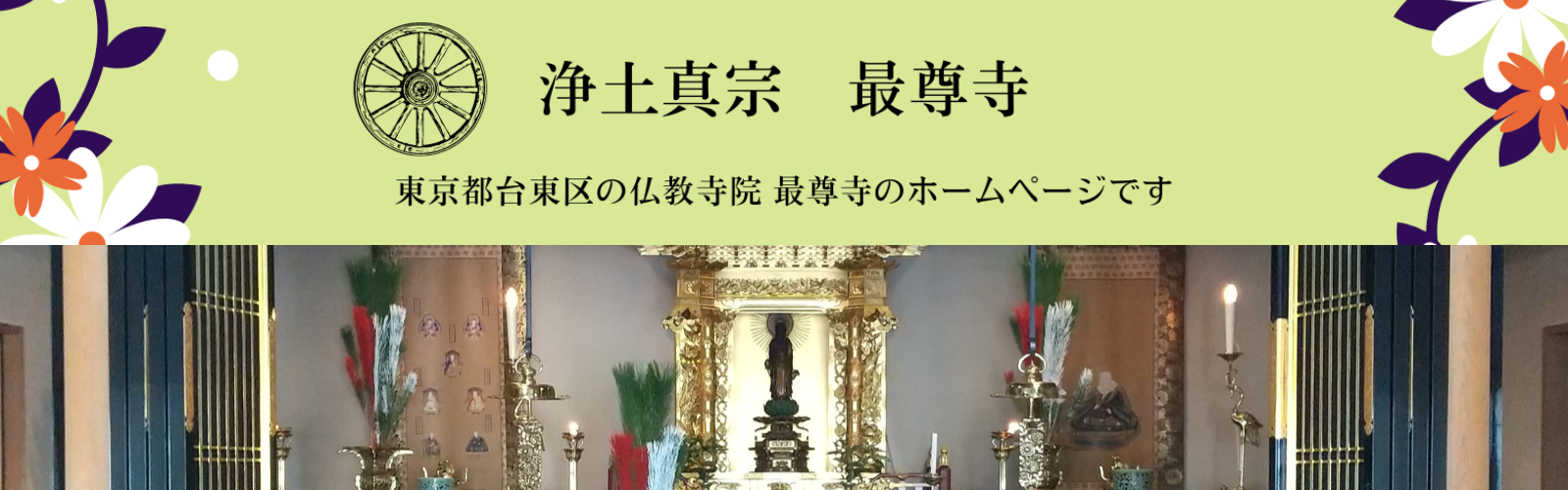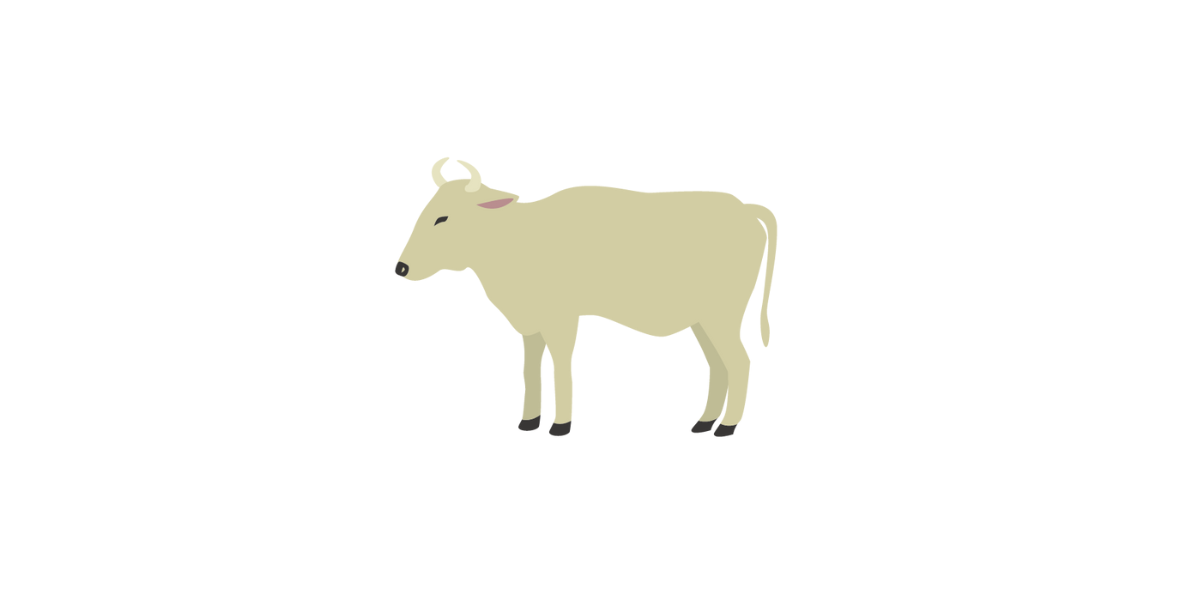紀元前(今から2000年以上前)に作成されたと考えられている『ミリンダパンハー』というお経があります。
このお経は、仏教僧ナーガセーナと、当時、西北インドの国王であったミリンダ王(メナンドロス王)の対論集です。
ミリンダ王は実在する人物で、王がデザインされた貨幣なども発掘されています。
ミリンダ王はギリシア系の人物で、紀元前2世紀ころ、西北インドに彼の支配していた国がありました。
さかのぼること紀元前4世紀、ギリシアのアレクサンドロス大王が現在のインド付近まで東方遠征を行いました。
面白いことにその影響で、当時のインドの西北部には、いくつかのギリシア系の国があったようです。
『ミリンダパンハー』は、そのミリンダ王が仏教僧ナーガセーナと対論し、あらゆる点からナーガセーナに論破され、仏教に帰依をするというお話です。
ミリンダ王は実在する人物ですが、ナーガセーナという仏教僧が実在したのかは分かりません。
『ミリンダパンハー』は後世、仏教側が仏教の教えを広めるために創作したものである可能性もあるでしょう。
いずれにしても、ミリンダ王が実在した時期より後、紀元前後には作成されたのだと想定されます。

この対論集の中で、「念仏」による功徳を説く箇所があります。(以下要約)
ミリンダ王:「尊者ナーガセーナよ、あなたは『百年間、悪いことをしても亡くなるときに一度でも念仏をすることができたら、その人は(念仏の功徳により)天に生まれると言う。私はこれを信じません』」
ナーガセーナ:「大王よ、あなたはどう思いますか? たとえば小石は舟がなくても水に浮かぶでしょうか?」
ミリンダ王:「尊者よ、そうではありません」
ナーガセーナ:「大王よ、荷車100台の小石でも、船に乗せたら水に浮かぶでしょうか?」
ミリンダ王:「尊者よ、そうです。水に浮かぶでしょう」
ナーガセーナ:「大王よ、良い行い(念仏)は舟にように見られるべきです」
ミリンダ王:「尊者ナーガセーナよ、その通りです」※1
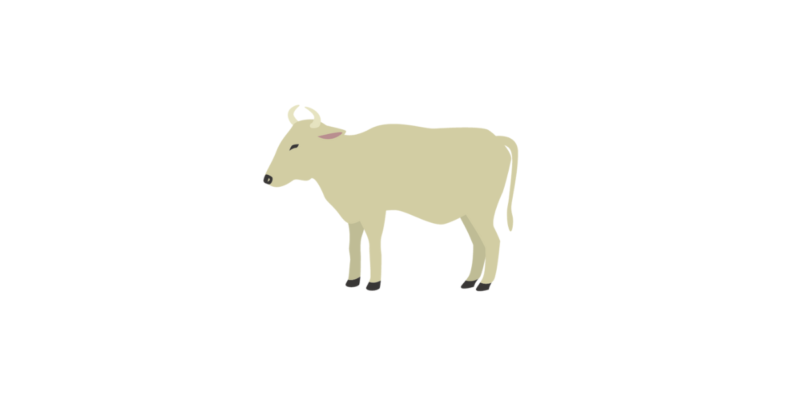
ここでは、悪い行いが小石に、念仏の功徳が舟に例えられています。
『ミリンダパンハー』という対論集は、小さな話をたくさん集めてまとめられたものです。
上記の話もとても小さなお話で、前後の話との関係があるわけではありません。
「悪いことをしても大丈夫」という意味ではなく、ただ、念仏がいかに有益であるか、素晴らしい効用があるかを示すための小さなお話です。
また、この念仏に対する考え方は、あらゆる地域・時代の仏教に共通しているというわけではありません。
分かるのは、仏滅後数百年経った2000年前のインドにおいて、念仏の功徳とそれにより天へ向かうという考えが伝わり、保持されて、『ミリンダパンハー』という仏典に描かれているということです。
これが直接、後世の浄土思想の源流であるかはわかりませんが、そのような考えが当時、仏教徒の中で根付いていたことが伺われます。
(注・補足)
(1)Milindapañho, PTS, pp.80.