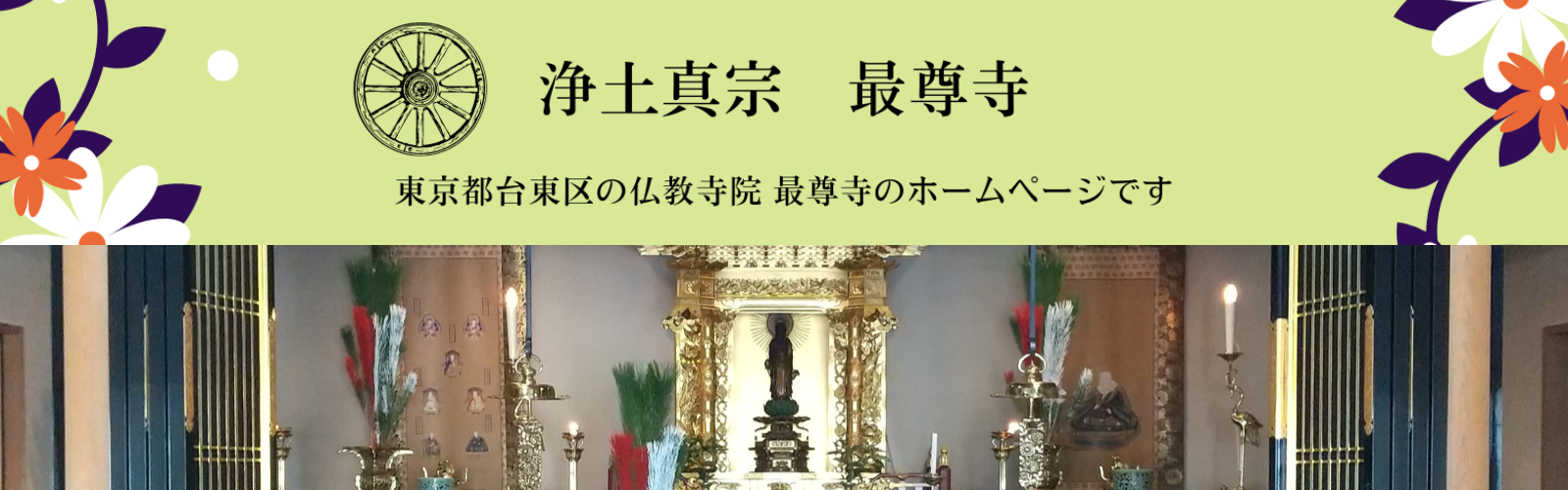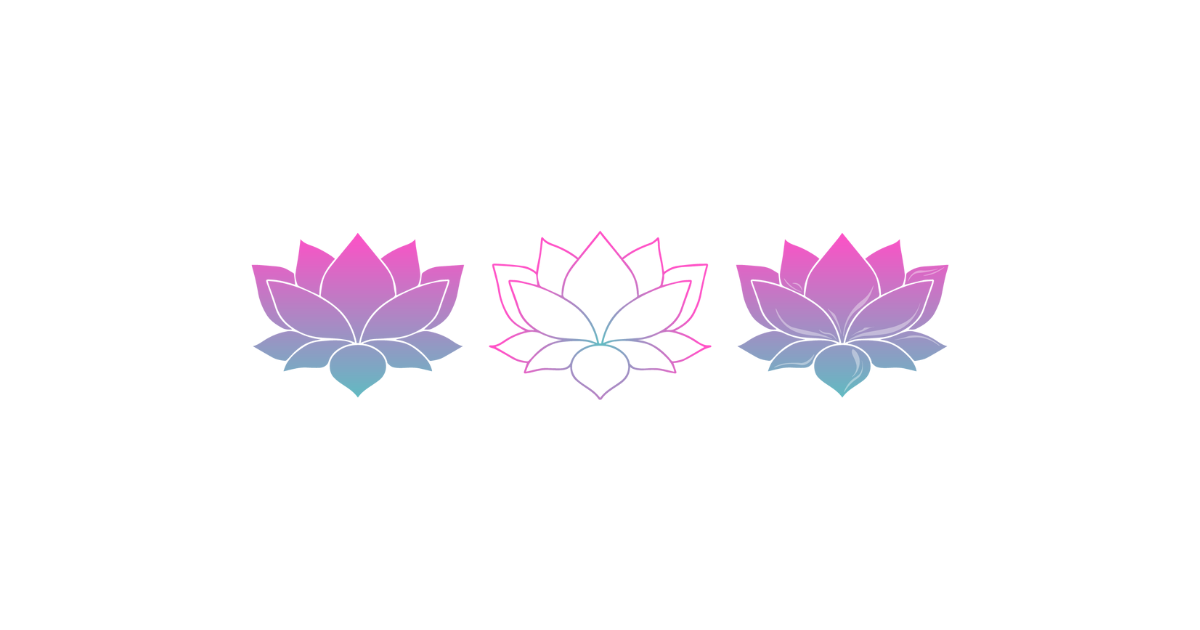古代のインドにおいて、「占い」などはあったのでしょうか。
現代の日本においては、星占いや血液型占い、現世利益を求める儀式など、さまざまなものがあります。
神社などにおいても、手を合わせて願い事や祈願をされる方は多いと思います。
お寺やお墓などでも、そのようにされている方は、たくさんいらっしゃると思います。
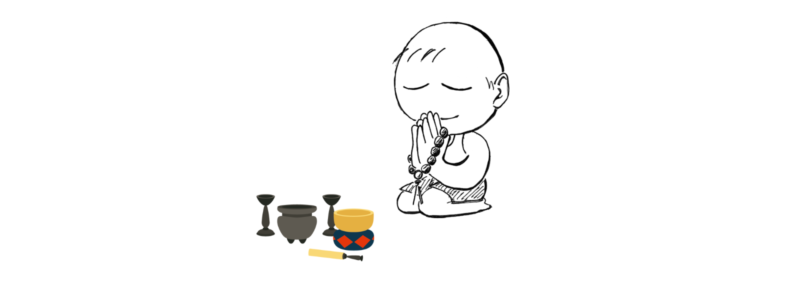
古代インドの初期仏典には、当時の「占い」や「呪文」と思われる記述が出てきます(1)。
どのようなものがあったのか、いくつか挙げますと
夢占い
ネズミが(人を)噛む場所による占い
鳥の鳴き声による占い
火への祈祷
悪魔払いの呪文
毒を消す呪文
蛇にかまれたときの呪文
宝石の様相による占い
衣服の様相による占い
剣の様相による占い
男・女性の様相による占い
少年・少女の様相による占い
奴隷の様相による占い
象の様相による占い
などなど、さまざまな「占い」や「呪文」が登場します。
このような「占い」や「呪文」などによって、生計を立てていた人々がいたようです。
またその他に、戦争を占ったり、星の動きや天候を占ったり、幸・不幸をもたらす呪文や火を吐く術なども登場します。
現代と比べても、多種多様な「占い」や「呪文」が登場します。
古代インドの人々は現代の私たちよりも、目の前の不可解な世界に対して「占い」などを頼りに日々の生活を送っていたのかもしれません。

仏教において、上述の占いなどはどのように考えられていたのでしょうか。
初期の仏典においては、仏教の出家者(比丘)に対し、これら「占い」などはすべて「畜生の呪術」であり「邪悪な生活の営み」として離れるように、と説かれています。
しかし同時に、それらを否定していないような文脈もあり、ある種の護符のようなもので良い果を得る話もしばしば登場します。
後世の仏教の進展においては、これら占いなどに対して様々な考え方が登場します。
あくまで初期の仏典の基本的な考え方としては、出家者はこれら「占い」「呪術」などで生計を立てることは禁じられ、また離れるように説かれています。同時に、経典には仏教の念仏やある種の言葉などにより、良い果を得るような内容も散見されます。
仏教において、どのような占い・呪文のようなものが認められ、認められていなかったのか、正確なところは、よくわからないのです。
(上記の話は出家者に関することです。当時の仏教の在家信者は、占いなどに対してどのように対していたのかは不明です。経典は基本的に出家者に対して説かれたものであり、多くは出家者へ対して語る内容なのです)
(注・補足)
(1)Dīgha-Nikāya Ⅰ 13.