初期の経典に「尼僧の詩(偈頌)」(Therī Gāthā)というものがあります。
古代インドの尼僧による、様々な苦しみや喜びの詩です。(岩波文庫『尼僧の告白』中村元 は日本語訳でお勧めです)
その中で、尼僧パターチャーラーは、子を亡くし嘆き悲しむ女性に対して、下記のように説きました。
[亡くなった]その子が来た道、去った道を、
また、その子がどこから来たのかも、あなたは知らないのに、あなたは『私の子よ』と悲しむ。
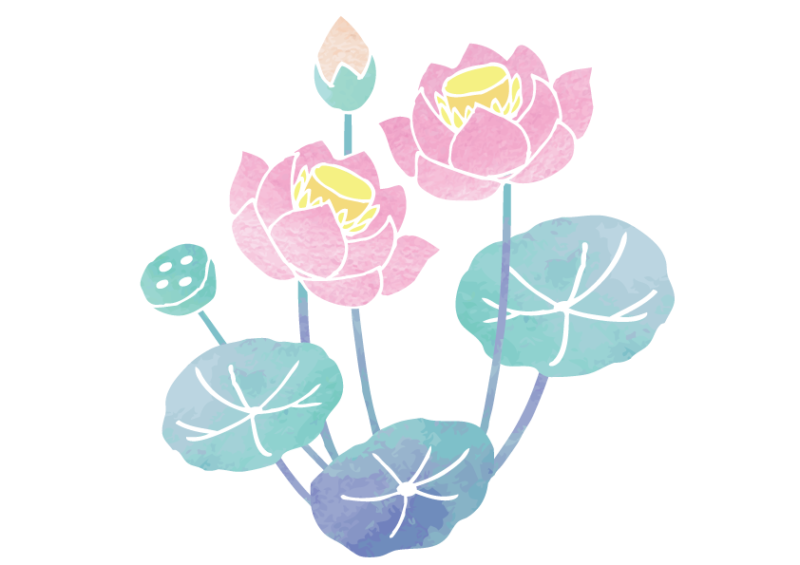
しかし、[その子]が来た道、去った道を、あなたが知っているのなら、あなたはその子[の死]を嘆かない。実に、生き物は[死ぬという]そのような定めを持っているのです。
[その子は]求められていなかったのに、そこから来て、許されていなかったのに、ここから去った。どこからかやって来て、また確かに数日間[ここに]住んで。
[その子は]ここから異なる[道を通り]やって来た。[その子は]そこから異なる[道を通り]去るだろう。
人の形をした亡き霊として、「輪廻」しつつ去るだろう。
来たときのように去った。そこに何の悲しみがあるだろうか。(1)
尼僧パターチャーラーはこのように説き、女性は悲しみが癒え仏教へ帰依したそうです。
古代のインドは、生きることが非常に厳しい環境であったと想像できます。
災害や戦争、病気や飢饉、盗賊なども常に身近な問題であったと思われます。
生命の流転は、今とは比べられないほど「無常」を感じさせるものだったでしょう。
仏典には、人の体を「蛆(ウジ)の城である」という表現があります。
当時は、遺体が墓地や通りにそのまま放置されることもあり、高温多湿のインドですから、そのような表現が生まれたと想像できます。
人々は、生命の流転を目の当たりにしながら日々生きていたはずです。
そのような環境の中で、亡きわが子を嘆き悲しむ女性に対し、尼僧パターチャーラーは上記の詩を説いたようです。

「来た道、去った道を知らない」「その子がどこから来たのかも、あなたは知らない」とは、「輪廻」の思想が前提にあります。
どのような経緯で「輪廻」し、「その子」はここに来て、どこへ去ったのか……。
「その子」は「輪廻」しつつ、来たときのように去っただけであると。
それは仏教の教えである「無常」(常であるものは無い)ということでしょう。
このように、無始である大きな「輪廻」の中で、「その子」はどこからか来て、そのまま去っていった。それは生き物の定めである、と説きました。
(注・補足)
(1)Therī Gāthā , PTS, p.136.



