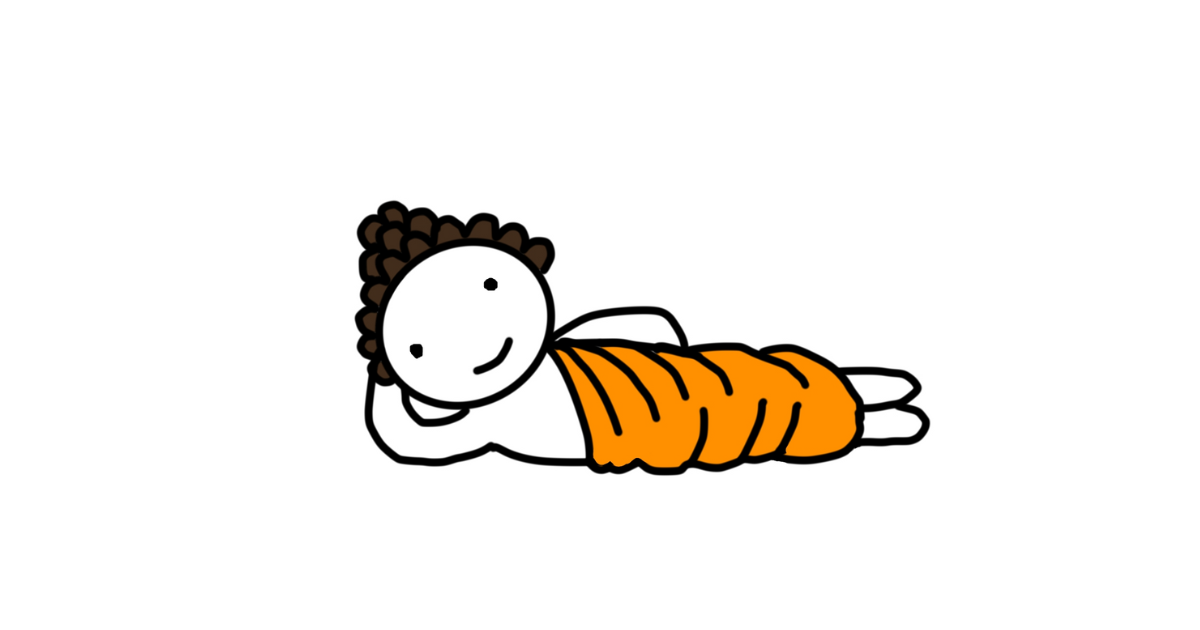「輪廻」(りんね)という言葉があります(輪廻転生とも)。
生命は終わると「輪廻」し、生前の行為に応じて次の生命へ生まれ変わっていく、というものです。
生まれ変わる行先としては「天・人・阿修羅・畜生・餓鬼・地獄」の六つあり、「六道輪廻」ともいわれます(経典には阿修羅のない五道輪廻もあります)。
初期の経典にこのような話があります。
「比丘たちよ、この長い[輪廻の]時間のなかで、以前に母でなかった生き物を見つけることは簡単ではない」(1)
続いて、父、兄弟、姉妹、息子、娘と同じ内容が続きます。

By Nagarjun Kandukuru from Bangalore, India – The wheel of life,
CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48976208
「輪廻」は際限なく続くため、目につく生き物はすべて、自分のかつての母や父であったというのです。
例えば、目の前のいる一匹の虫も、かつての自分の母であり、父であり、子であったと。このような世界観を持っていたことは、とても興味深いことです。
このように、インドにおいて、生命は「輪廻」するという考え方が土台にありました。経典には、頻繁に「輪廻」について説かれています。
インドの思想において、基本的に「輪廻」は苦しみであり、仏教含め多くのインドの思想や宗教では、そこから脱すること(解脱)を求めたのです。それは至上の安らぎともいえる境地でした。
「輪廻」という考え方は、元は「ヴェーダ」の中にある「五火二道説」(ごかにどうせつ)という説から発展した、ともいわれています。
「五火二道説」では、生命は亡くなると火葬され、登って月へ行き、雨となり地に戻り、植物から食べ物となり、男から女へとつながり胎児となる、と生命の生まれ変わりが説かれています。
そして、生まれ変わりを繰り返し、人間へとなる道と、「輪廻」から脱し天へと向かう道の二つの道があるというのです。
「輪廻」については、「ヴェーダ」の説だけではなく、当時の諸民族の文化や思想からの影響があったという説もあります。いくつかの考えや風習などが混ざり合い、次第に「輪廻」となったのではないでしょうか。
ともあれ、お釈迦さまが存在した当時のインド人々にとって、「輪廻」は常識のようなものだったのでしょう。(その常識にとらわれず「輪廻」を否定する修行者たちもいました。)
いずれにしても、この「輪廻」という考え方は、仏教の教えにとって大前提となるものです。
仏教においては、生きることは苦しみであるという前提のもと、戒律を守り、修行に励み、学び、「輪廻」から脱する「解脱」を最大の目的としました。(2)
(注・補足)
(1)Saṃyutta-Nikāya Ⅱ, PTS, pp.189-190.
(2)昔から、お釈迦さまは「輪廻」を否定したという説も多くあります。
例えば昭和初期、宇井伯寿氏や和辻哲郎氏が非常に現代的な仏教理解を展開し論争になったり、不可触民開放運動のアンベートカル氏も古代インドンの文脈から離れて、自身と現代に適合した理解をしました。主に、「現代に残る仏典は後世の創作・付加が多く仏陀の真意ではない」という考え方や、仏典に説かれる教えに現代的な整合性を求めたい気持ちが土台にあるように思います。
初期仏典は現代的な理解からすると整合性を欠く面も多く、(凡夫の私から見ると)矛盾も多く見受けられます。「輪廻」と「無我(非我)」は矛盾している、という多くの議論があります。
仏典は、仏法というよりは当時の社会の道徳を説いたものもありますし、後世の付加や改変、後世の語り部の大衆へ向けた誇張もあったでしょう。しかし、「輪廻」などの古代インドの文脈から離れてしまうと、「比丘たちよ」と出家僧へ語った経典の多くの意図や世界観が崩れるように思います。比丘たちへ語る「業」や「輪廻」、それを土台とした各種の伝統的な修道などが、便宜的な道徳や後世の付加とは考えにくく感じます。後世、仏教学において「姉妹宗教」といわれた「ジャイナ教」では、明確に「輪廻」からの離脱を教義の根本に置いています。
しかし同時に、当時、堂々と「輪廻」を否定した修行者もいました。当時は修行者同士の討論も盛んだったようです。お釈迦様はそれを知りながら、とても論理的な思考を持ちつつ、どのような考えで伝統的な「輪廻」をそのまま受け取ったのか、真意を知りたく思う気持ちもあります。
こればかりは、本人に聞かないとわかりません。